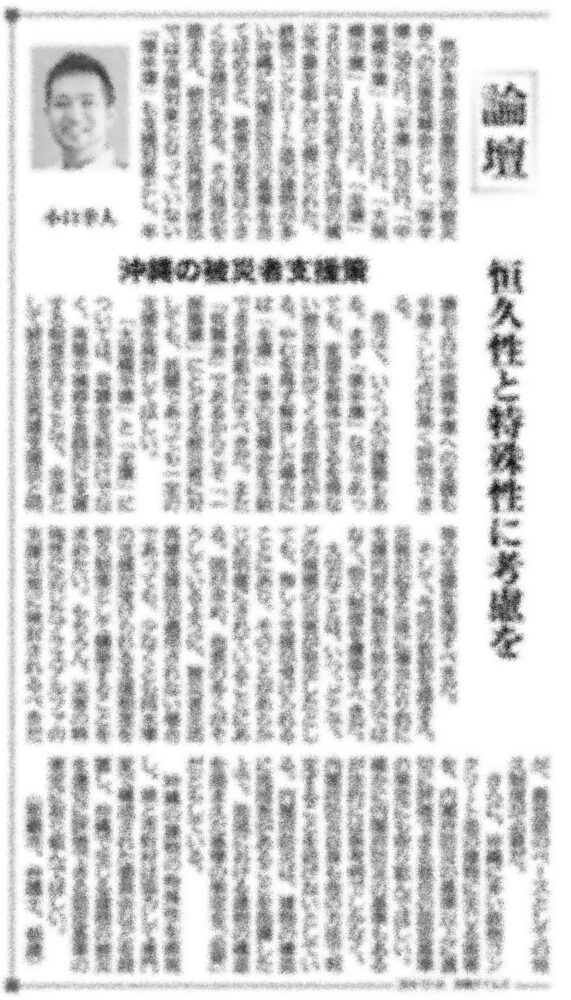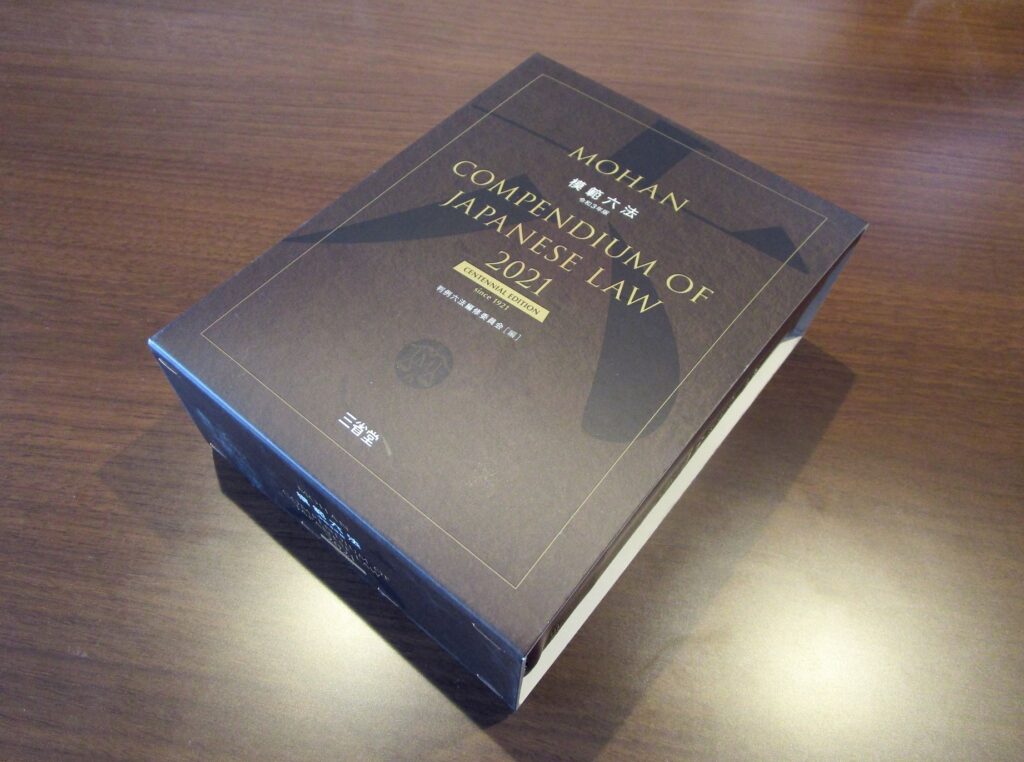
2023年9月12日、最高裁判所第三小法廷において、歴史的な最高裁判決をいただきましたので、後のためにも、報告させていただきます。
第1 実質勝訴
今回の裁判は、国家賠償請求訴訟、つまり、損害賠償の形をとっていますが、国からお金を取りたいから、この方法を選択したのではありません。過去に例のない裁判であるところ、訴訟要件に問題がない方法として、便宜的に、この形を選択しました。そのため、請求額はたった1万円としました。
お金ではなく、何が目的だったのか。それは、次の三点です。
ア 憲法53条後段が定める内閣の臨時国会召集決定義務は、政治的な義務や訓示規定ではなく、法的義務であることを明確にしたかった。
イ 合理的期間だけでは不十分なので、何らかの日数、数字を示してほしかった。
ウ 次に同じこと、つまり、憲法に基づく臨時国会召集要求がされたにもかかわらず、内閣が、与党と相談して決めるなど、すぐに召集しようとしなかったときの解決手法を示してほしかった。
9月12日の裁判では、無事、三つの目的を全て達することができました(詳しくは後述)。よって、敗訴と報道されていますが、勝訴、厳密には実質勝訴という受け止めをしています。
このことは、例えば、国の主張が、全くと言っていいほど、裁判所に採用されていないことからも明らかです。国の主張は、主に次の四つでした。
あ 高度に政治的な統治行為だから、司法権の範囲外である。
い 「あ」でなかったとしても、法律上の争訟ではないから、裁判所が判断することは許されない。
う 憲法53条後段が定める義務は、政治的な義務であって法的義務ではない。
え 国会議員一人ひとりが、個人の損害賠償を請求できるような件ではない。
最高裁判所は(他の6の地裁高裁もそうでしたが)、「あ」の俗にいう統治行為論を排斥しました。特に最高裁は、触れもしないで一蹴しました。
「い」について、最高裁判所は、東京高等裁判所の判決を正しいものではないとして、法律上の争訟であると判断しました。
「う」についても、最高裁判所は、他の6の地裁高裁と同じく、法的義務であると判断しています。
唯一国の主張が受け入れられたのは、「え」の部分だけですが、冒頭のとおり、元々こちらも、お金目当てではありませんでしたので、どうということはありません。ほかに争う方法があるなら、今後は、国賠の方法をとる必要もありません。
なお、国は一貫して98日後の臨時国会召集決定は、合理的期間内であるから、合憲合法であるという主張をしませんでした。那覇地方裁判所では、裁判官から、そういう主張はしないのかという釈明がされ、国は持ち帰って検討しましたが、次の期日で、その主張はしないと明言し、最後まで(最高裁まで)一度もしませんでした。
裁判所で、合憲合法だと主張すらできない行為を政府がしていたこと、そして、裁判所ではそのような対応をとっておきながら、記者会見等では合理的期間内だと説明し続けた点は、誠に情けない話だと思っています。
第2 次のときの解決方法
1 将来の流れ
わかりにくいと覆いますが、第1でいくつかでてきているように、裁判所では争えることと争えないこと、裁判所が判断できることとできないことがあります。
そして、法律の中には「訴訟法」というものがあり、どの訴訟法にもスパッとあてはまらない特殊な裁判をするときには、どうやって、その裁判を正当化するかという難しい問題があります。
憲法53条後段についても、内閣の義務が法的な義務であって、このような長期間の召集懈怠は許されないことは、憲法学説上、異論のないものでしたが、じゃあ、どうやって、裁判で争うのかという点がブラックボックスでしたし、裁判所では争う術はないのではないかという意見も多くありました。
しかし、今回の最高裁判決が示されたことで、次、内閣が同じようなことをした場合には、次の流れで是正されることが見込まれます。
A いづれかの議院の総議員の4分の1が臨時国会召集要求をする。
B 内閣が、速やかに召集決定をしないで、与党と相談してとか、審議する議案を検討して断すると、
これまでのように「のらりくらり」の応答をする。
C Aの召集要求に参加した国会議員(個人)が、東京地方裁判所に対し、行政事件訴訟法第4条に
基づき、公法上の義務確認訴訟として、内閣の臨時国会召集決定義務の確認訴訟を提起する。
D 裁判所は、間近い時期に通常国会or特別国会の予定があるか&天変地異や戦争が現に起きている
かのみを判断し、それがないのであれば、内閣に召集決定義務があると判断する(召集から20日とい
う目途の中で迅速判断がされる)。
なお、実際は、Cの訴訟提起が起こされると報道された時点で、臨時国会の召集決定がされるようになる、あるいは、訴訟が提起され裁判所が直ちに進行協議期日等が開かれ裁判所から「いつ召集決定するのですか」等詰められたことにより臨時国会の召集決定がされるようになり訴訟が取り下げられる、という流れになると思されます。
理由は次のとおりです。
2 法律上の争訟であるが確認の利益がないという意味
最高裁判所では、内閣の臨時国会召集義務の存否を争う裁判が、法律上の争訟であると判示されました。その上で、いま臨時国会召集要求がされていて内閣が懈怠しているわけでもないし、将来同じことが確実におきるわけではないから、いま裁判所で判断する意味、確認する利益がないという判断がされています。
これは、逆に言えば、現に臨時国会召集要求をして、内閣が懈怠しているときに裁判をすれば、確認の利益もあるということです。
そして、論理的に、確認の利益だけで排斥されたということは、今回の枠組み、すなわち、臨時国会召集要求に参加した国会議員個人が原告になるだけで足り、4分の1以上の国会議員全員が原告になるなどしなくても、原告適格が満たされることも今回の裁判ではっきりしました。
よって、上記1Cの裁判が、将来同じ問題が起きたときの解決方法が明確になり、ブラックボックスではなくなりました。
その上で、裁判の中身はというところについては、多数意見は何も示していませんが、恐らく将来それが起きたときに地方裁判所の裁判官が判断枠組みに迷うことがないよう、宇賀裁判官が、判断枠組みを丁寧に示してくれました。
ア 内閣が負う臨時国会召集決定義務は法的義務であること(異論がないと思われるという記載は、
他の4人の最高裁判事も同じ意見だった、という意味です)。
イ アについて、事務的に必要な最小限の期間内に召集する義務であることについて、「学説」でも
異論が「ない」こと。
ウ 例外は、間近に通常国会or特別国会の予定があるか&天変地異や戦争(単なる災害ではなく、
天変地異や戦争に限定されています)等に限られること。
エ 「ウ」の例外にあたらないなら、例えば、内閣が法律案提出の準備を理由として遅延させること
も許されないこと。
オ 「ウ」の例外に当たらないときの期間としては、「20日あれば十分」という考え方、20日以内に
召集する義務があると考えてよいこと。
そして、「ウ」の例外のケースに当たるかあたらないかは、誰の目にも明らかな公知の事実です。
よって、裁判所が、訴訟提起されるや否や、可及的速やかに、内閣に召集決定義務があると判断することは容易となり、しかも、20日という目途を反対意見ではあっても、最高裁判事が「20日あれば十分」という表現で示してくれましたので、裁判所としても、これは超特急で判断しなければならないと認識し、動いてくれるはずです。
3 20日以内の意味
確かに、20日という数字が示されたのは反対意見です。しかし、この意味はとても大きいと思っています。
数字は、独り歩きしやすいので、これまでの6つの地裁高裁も、期限を数字で、日数で示すことはしてきませんでした。控えてきた、という意味です。
そして、20が正しいか15が正しいか、それとも25なのかというのは、法解釈から導くことが、極めて難しいです。そのため、学説も幅を持った指摘しかされてきませんでした。数字を言い切り、そこに説得力を生じさせるには「権威」が必要です。
要するに、論理的に20が正しく15は間違っている、25は間違っていて20は正しいと言うことが難しい問題だから、えいやで、偉い人に決めてもらうことで、初めて説得力が出るわけです。
このように、地裁高裁判決も数字を示してこなかった状況下で、反対意見ではあっても、最高裁判事が「20日あれば十分」と、20と言い切ったのは極めて大きいです。これぞ、権威がなければできないこと、「最高裁判所」にやってほしいことでした(なお、3つの論拠が示されているのですが、これは、訴訟代人弁護士の主張がそのまま採用されたものです。)。
しかも、これぞ、権威がなければできないこと、最高裁にやってほしいことでした。
しかも、例えば「20日が目安」とか「20日程度」といった表現では25はどうだ?という議論が続きます。しかし、「20日あれば十分」という表現は25はもちろんダメと言い切れるので、表現方法としても素晴らしいと受け止めています。
よって、今後は、例えば10日だと主張することはできても、25だ30だと説得的に主張することは限りなく不可能になります。
今後は、政府内の検討の際も、報道の際も、そして、未来の裁判所も、誰もがこの20を意識した議論行動をとることになりますので、この意味で、宇賀裁判官が示した「20日あれば十分」という文言は、将来の様々な判断を、事実上拘束するのだと思います。
第3 政治に与える影響
最高裁判所が、今回の判決を示したことで、現実世界の政治、すなわち、国会にも大きな影響が生じると考えています。
少し考えていただきたいのは、国会って、昔は会期が少しは延長されていたのに、最近、全然延長されてないよね、ということです。
通常国会の会期は150日ですが、最後に延長されたのでさえ平成30年、つまり6年前です。その前は、平成27年の安保国会のときです。平成24年に安倍政権が誕生した後、通常国会の会期が延長されたのは、実に、この2回しかなく、後はすべて、1日の延長もなくして国会は閉じられています。
なぜそんなビシッと、延長なしで閉じるのかと言えば、審議等が打ち切られているからです。当然、野党の側は、臨時国会召集要求をしてきましたが、与党総裁=総理大臣という状況下で、内閣はこれを無視し、国会は開かれない、結局、打ち切ったもの勝ちという状況になっていました。
しかし、今回の最高裁判決により、国会を強引に閉じたとしても、野党が臨時国会召集要求を出したら、速やかに臨時国会を招集しなければならなくなりました。つまり、強引に閉じても、得られる猶予期間は短く、次は臨時国会で、強引に閉じたことも含めて厳しい追及がされるということになりました。
与党の側に、国会を強引に閉じる「旨味」が減り、会期を延長しないという方法では追及を逃れることができないとなった以上、ある程度、野党が求める調査等を行うとしてその間会期を延長するなど、一定程度、野党の要望を踏まえた国会対応と会期の延長等がとられやすくなります。
また、時間稼ぎによる追及逃れができなくなった以上、ひたすら国会議員の質問にゼロ回答を繰り返すという方法では足りず、ある程度は質問に答え、最低限の野党の納得感を得られるように応答しない限り、国会が終わりにならないということを、政府与党は考えながら国会運営にあたるようになるはずです。
私はこの現象をオセロの角に例えています。オセロでは、角をとった方が強いので、相手に角をとられないようにします。そうすると、角の一つ外側のマス、その次は、さらに一つ外側のマスをどちらが取るか(相手に置かせるか)の攻防になるわけです。
今回の最高裁判決により、強引に国会を閉じたところで臨時国会を招集させられるから意味が乏しいことが示されたことにより、国会を閉じる前の与野党のやりとりや、それに先立つ国会審議の中身にも栄養が生じ、政府が質問に答える、はぐらかすだけではない国会に、少しずつ近づいていくのではないかと、そんな淡い期待を抱いています。
第4 責任は一定程度果たされた
最高裁判決を批判する定型句として、司法が責任を放棄した、という文言があります。しかし、今回、最高裁判所は、ある程度ではありますが、責任を果たしたように思います。
法的義務であることをはっきり示し、次同じ問題が起きたときの解決方法も示し、20日という数字も説得的に示されたからです。
もちろん、国家賠償請求が満額認められた方がよかったですし、反対意見を書かれた宇賀裁判官が、こちらの請求を満額了解してくださったことは大変光栄ですが、上記の限度でも、裁判をした価値は十分にあったと思っています。
憲法53条後段は、憲政史上、ずーっと蔑ろにされてきました。宇賀裁判官が次のように、過去の内閣の対応を「これでもか」というほど批判したとおりです。
「記録によれば、憲法53条後段の規定による臨時国会召集要求のうち20日以内に召集されたのは40回中5回しかなく、かつ、過去3年間をみても、臨時国会召集決定は臨時国会召集要求から20日を大きく超えてから行われている。このような事態が生じているのは、臨時国会召集要求がされた場合、内閣として臨時国会で審議すべき事項等も勘案して、召集時期を決定する裁量があるという認識があるからと思われ、そうである以上、令和5年ないし令和6年に臨時国会召集要求がされて、20日以内に臨時国会が召集されない蓋然性は相当に高いと思われる。」(*1)
ぜひ、内閣にはこれまでの対応を猛省してもらい、しっかり今回の最高裁判決を受け止め、次臨時国会召集がされたときには、与党と協議とか、法案の検討などと言い訳するのではなく、事務的に必要な最小限の期間内に可及的速やかに臨時国会を召集してほしいと思います。
もしそうならないなら、直ちに、内閣の召集義務確認訴訟が提起されるだけですから。
■ 最高裁判所令和5年9月12日憲法53条違憲国賠訴訟判決(PDF)
*1)参考までに衆議院における国会会期一覧のURLを以下貼り付けます。
衆議院_国会会期一覧









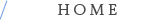

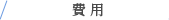

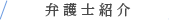
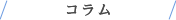
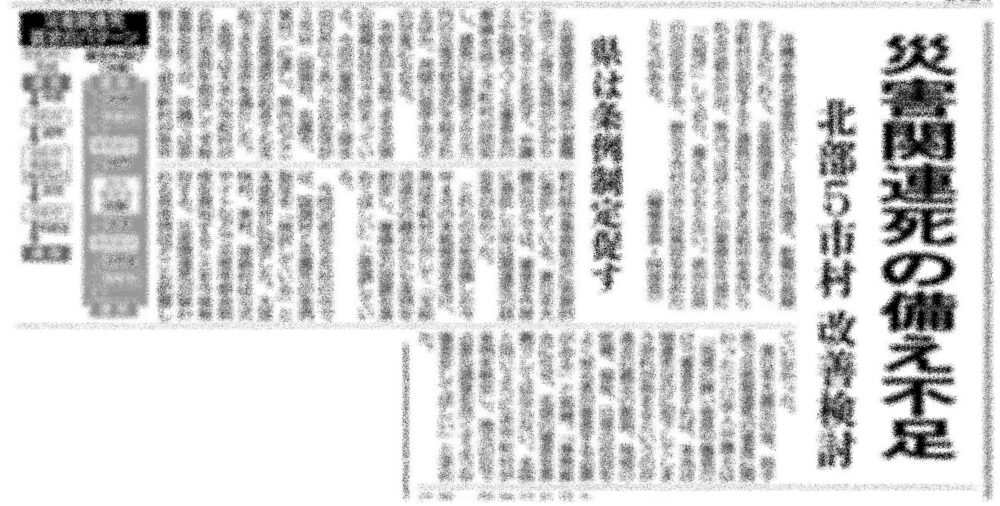
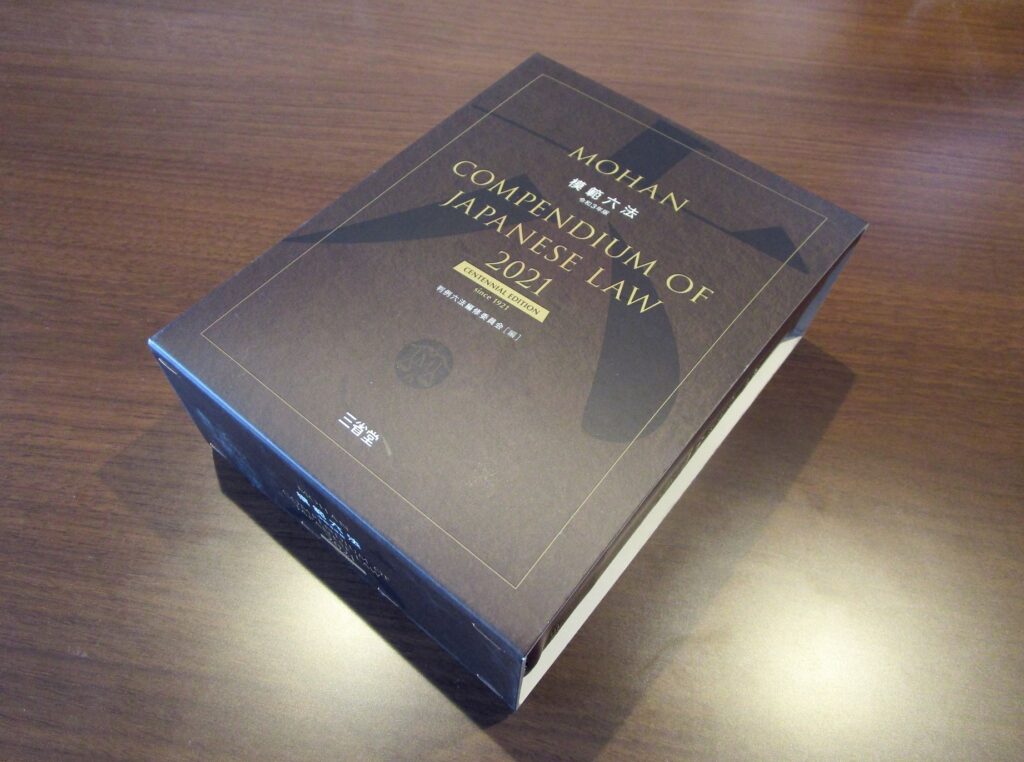



 今、憲法改正の本命に浮上している、緊急事態条項の「国会議員の任期延長」について、
今、憲法改正の本命に浮上している、緊急事態条項の「国会議員の任期延長」について、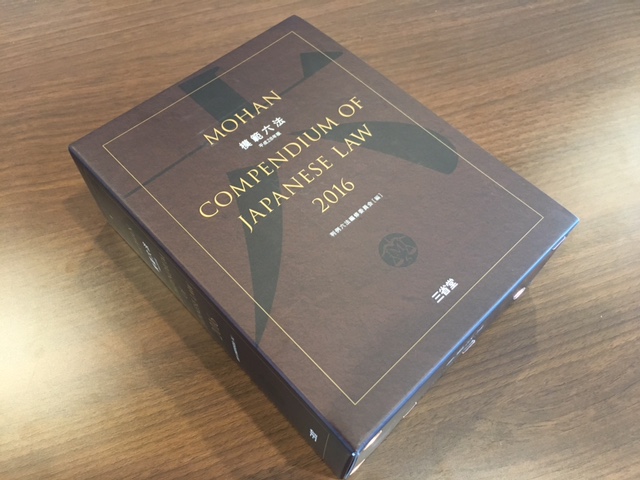 2022年8月30日に、東京の国会議員会館で記者会見を開いてきました。
2022年8月30日に、東京の国会議員会館で記者会見を開いてきました。 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。